小学生のときの遊びは、今思い出してもホントに画期的でおもしろかった。
これらの遊びは果たして全国的に流行ってたのか、今でも遊ばれてるのかわからないけど、いくつかご紹介しよう。
ドッジボール
小学校1、2年のときの休み時間はほぼこれに費やされた。
給食を胃に流しこみ、ボールを取ってグラウンドの場所取りのためにダッシュしたっけ。
ちょうど「くにお君のドッジボール」というファミコンのゲームも流行ってた。
今考えて不思議なのは「ライフ」的なシステムがあったこと。
つまり、自分が相手をひとりボールで当てたらライフは1ポイント増える。
そのライフのことを「き」と言っていた。
マリオでもライフが増えることを「いっきアップ」と言ってたし、ドラゴンボールも「き」を使うので、当然のように「き」を使っていた。
しかも斬新なシステムが、この「き」は同じチームで振り分けることができるのだ。
「オレ5きあるから、いっきあげるわ。」という交渉がコートの中で行われる。
今、思えばそんなのいくらでも嘘つけるけど、嘘をつくなんていう概念は誰もなかった。
ろっくん
小学校3年あたりになると、ドッジボールは卒業してさらに戦略性の高い遊びに移行する。
それが「ろっくん」である。
15メートル間隔くらいで2つの円を地面にかく。
学校以外ならマンホールが丁度良い感じの間隔だったのでそれを使った。
この2つの円の前に鬼が1人づつ立ち、中の人はこの2つの円を行ったり来たりする。
鬼はそれを阻止すべくボールを当てるという遊びである。
むこうの円まで行くことを「半くん」といって、往復すれば「いっくん」、もう1度むこうの円までいけば「いっくん半」、帰ってこれば「にくん」となる。
始めは「にくん」から。
「に~くんか~いし」とみんなで叫ぶことがスタート合図となる。
誰かひとりでもボールを当てられずに「にくん」を達成すれば、当てられた仲間はまた生き返り、次は「よんくん」に挑む。
「よんくん」「ろっくん」「はっくん」「じゅっくん」と「にくん」づつ増えていく。
「じゅうろっくん」くらいまではやった記憶がある。
当て鬼
もう少し学年が上がれば次は「エキサイティング」さをもとめるようになる。
そこで流行ったのが「当て鬼」
ルールは単純で鬼にボールを当てられたら交代するという、鬼ごっこみたいなものだ。
場所も校舎のまわりや、体育館のある別館を使ったり、広大なスペースで繰り広げられた。
最後にひとこと
もちろんサッカーやバスケなんかもやったし、「てんか」「ぴんぽん」といった少人数でできる遊びも楽しかったけど、小学生の頃を思い出すとこの3つがとても印象深い。
そして遊びのなかで何か都合が悪くなると「ちゅーき!ちゅーき!」といってタイムをとるやつもいた気がする。
今思えば、ちゅーきってなんやねん。て感じだけしその頃は「タイム=ちゅーき」だったのだ。
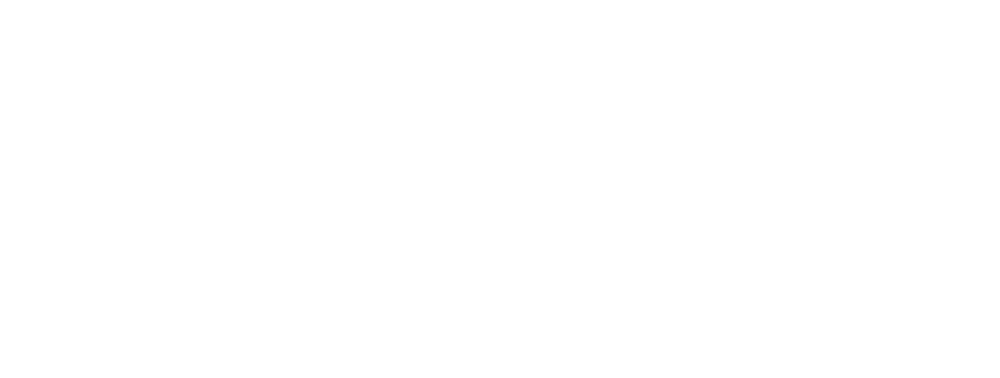


こんにちは